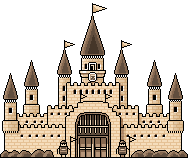<ぶらり 江の島>
江の島は、神奈川県藤沢市にある湘南海岸から相模湾へと突き出た陸繋島。
「えのしま」という地名ですが、
地図や住居表示はひらがなの「の」を使っているのに対し、
郵便局や交通機関はカタカナの「ノ」と混在していますし、
古くは「江島」などと書かれていたようで、
有名な「江島神社」はこの表記になっています。
<江島神社>
安芸の宮島、近江の竹生島とともに日本三弁天とされる。
欽明天皇13年(552)に岩屋(御窟)に神を祀ったのが始まりです。
日本三大弁財天を奉る江島神社は、
田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、
市寸島比賣命を祀る「中津宮」、
多紀理比賣命を祀る「奥津宮」
の三社からなる御社です。
<生しらす>
江ノ島がある神奈川県では、資源保護の目的で
毎年1月から3月中旬までしらすの漁を禁漁期間としています。
おいしい「生しらす」が食べられる時期は、
漁獲量の多い4〜5月、、7月、10月。
とくに10月は1日2〜3回も出漁する
ので、生しらすがたっぷり楽しめます。

※久しぶりにリフレッシュできました!
|

青銅の鳥居 |
江の島弁財天信仰の象徴である
青銅の 鳥居が創建されたのは
延亨4年(1747)。
現在のものは、
文政4年(1821)に再建され たもの |

朱の鳥居と瑞心門 |
朱の鳥居の正面、石段を上ったところにある
龍宮城を模した楼門
 |

辺津宮 |
建永元年(1206)に
源実朝が鎌倉幕府の繁栄を祈って創建。
現在の建物は延宝3年(1675)の再建、
昭和51年(1976)に改修されたもの。
 |

奉安殿 |
辺津宮の南隣にある八角円堂。
「裸弁財天」とも呼ばれる
妙音弁財天像と八臂弁財天像を安置している。
妙音弁財天像は琵琶を抱えた全裸の坐像。
女性の象徴 をすべて兼ね備えているといわれ、
鎌倉時代の傑作と名高い。
|

中津宮 |
江の島の中腹にたたずむ朱塗古社。
仁寿3年(83)に慈覚大師によって
創建されたといわれている。
現在の権現造の社殿は元禄2年(1689)に
再建されたも ので、
平成8年(1996)には大改修が行われ、
朱塗りがいっそう鮮やかになった。 |

奥津宮 |
三つのお宮には、三姉妹の女神様が祀られ、
ここ奥津宮には一番上の姉神の、
多紀理比賣命が祀られています。

「八方睨みの亀」 |

龍宮 |
奥津宮の隣にあり、
岩屋本宮の真上にあたるところに
平成五年(1993年)、
崇敬者の御篤志により建てられたお宮 |

岩屋 |
江の島弁財天信仰の発祥の地。
多くの高僧や武将がここを訪れて
祈願のため籠ったことを
「江の島参籠」といってました。
  |

恋人の丘「龍恋の鐘」 |
相模湾を荒らした邪悪な五頭龍を
江ノ島に舞い降りた天女(弁財天)が改心させ、
五頭龍は天女に恋をして結ばれた、
という江島縁起「天女と五頭龍伝説」
の恋物語にちなんで造られたもので、
その伝説にあやかり、
多くの人が鐘を鳴らしに訪れます
|